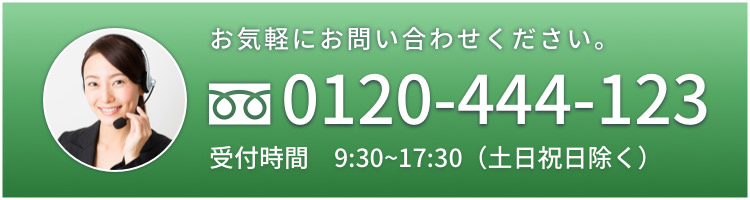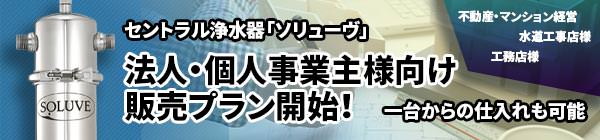【PFASの健康影響と論文差し替え問題】 食品安全委員会の評価プロセスを問う
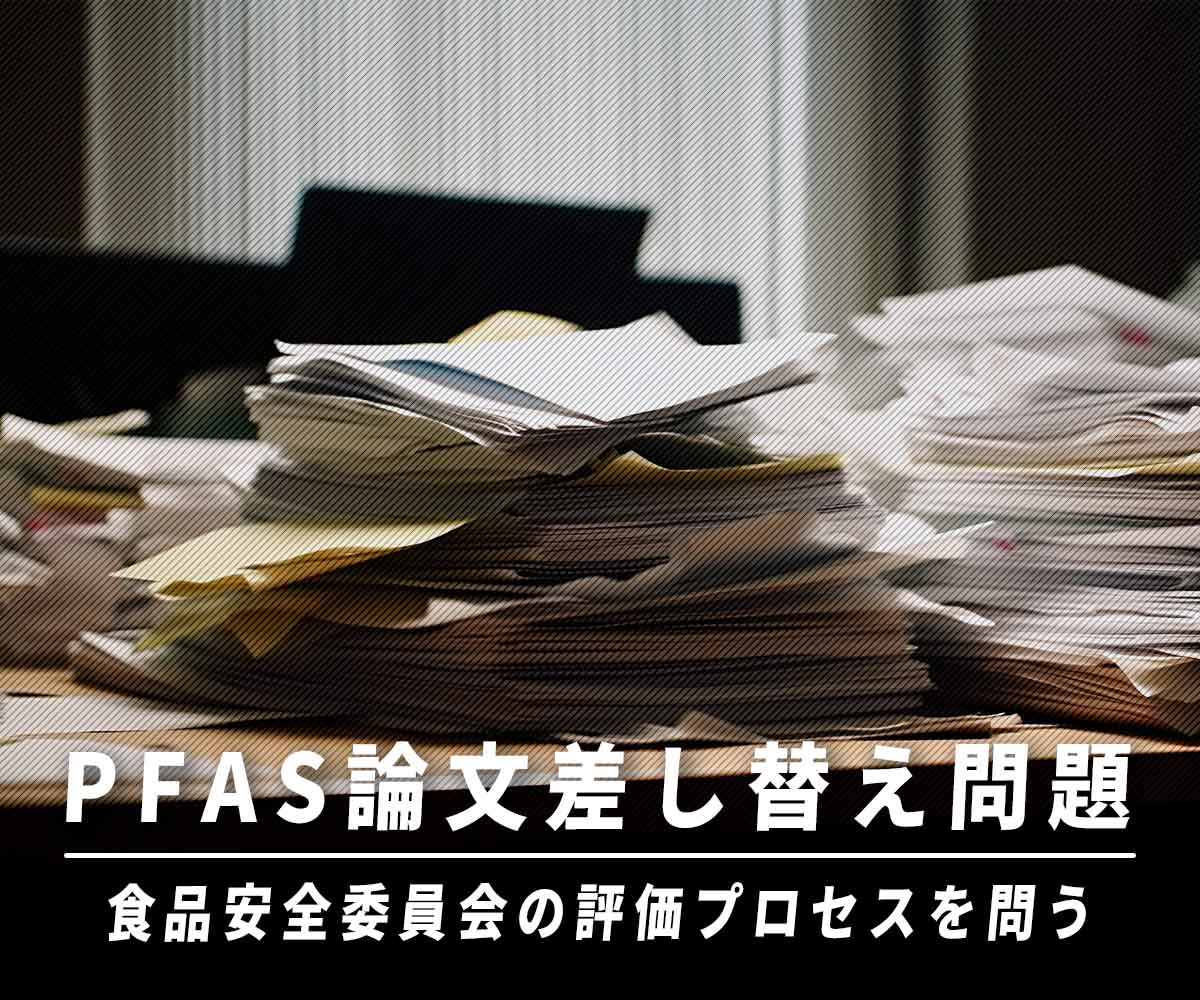

「国のPFASの評価基準の元となる論文の選定プロセスに問題があるというニュースを見ました。」
「確かに気になりますね。では、解説します。」



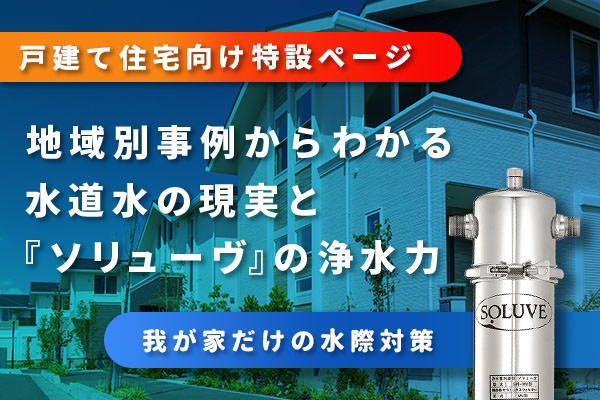

まずは自己紹介
弊社、株式会社メイプル・リンクは、創業33年のセントラル浄水器メーカーです。セントラル浄水器『ソリューヴ』の企画・製造・販売を行なっております。長年セントラル浄水器の販売を行なっている弊社が、気になる疑問についてお応えします。
論文差し替え問題とは
国が2024年に公表した有機フッ素化合物=PFAS(ピーファス)の健康リスクに関する評価書について、“市民科学” の視点から環境問題などの解決を目指す東京のNPO法人が3日会見し、評価書は作成過程で7割以上の参考文献が差し替えられていて科学的合理性を欠くとした検証結果を発表しました。
内閣府の食品安全委員会は2024年に初めてPFASの健康リスク評価書を公表し、1日に摂取しても健康に影響がないPFOS(ピーフォス)とPFOA(ピーフォア)の量について、体重1キロ当たり「20ナノグラム」と設定していました。
会見したNPO法人「高木基金」のPFASプロジェクトによると、この耐容1日摂取量20ナノグラムは、米国基準と比べて200倍から666倍高い数値です。
TBS NEWS DIG 「PFASの健康リスク評価 検討過程で参考文献の7割を差し替え 国の食品安全委員会「国側の意向でない」と恣意性を否定」より引用
健康影響が懸念される有機フッ素化合物(総称PFAS(ピーファス))をめぐり、内閣府食品安全委員会が昨年6月に公表した評価書について、「作成の過程に疑義がある」とするリポートを市民団体がまとめ、3日公表した。
評価書は、PFASによる健康影響の有無などを検討した学術論文268本を参照文献として分析。「発がん性の証拠は限定的、ないし不十分」などと述べていた。
これに対し、認定NPO法人「高木仁三郎市民科学基金」のメンバーが記者会見し、当初の文献リストにあった257本のうち190本が検討過程で分析対象から除外され、リストになかった201本が新たに付け加えられていたとする検証結果を示した。
朝日新聞 「PPFAS評価書に「疑義」 市民団体が指摘、参照論文を大幅差し替え」より引用
私たちが毎日飲む水。しかしその水が「安全」だといえる基準の根拠を決める過程で、検討対象としていた論文が秘密裏に差し替えられていたとしたら、あなたはどう思うでしょうか。その水を安心して飲めるでしょうか。
国の食品安全委員会のもとで公開で行われた専門家の会議。ところが、基準を決めるための参考としていた論文の大半、190もの論文が密かに差し替えられていたのです。差し替えられた中には、海外では飲み水の基準を決めるにあたって採用されたり、発がん性に警鐘を鳴らしたりする重要な論文もありました。
SlowNews 「【スクープ】飲み水の基準の根拠を決める会合で評価のための論文が密かに外されていた!/シリーズ・PFAS論文差し替え疑惑①」より引用
参照:SlowNews 【スクープ続報】「腎臓がん」への影響、追加した低評価の論文1本で認定せず。「理想的な研究」とされた論文を差し置いて/PFAS論文差し替え疑惑③
参照:SlowNews 【スクープ続報】出生体重の低下、世界的に評価が定まり、否定する論文もないのに非公開の会合で採用せず/PFAS論文差し替え疑惑⑤
参照:SlowNews 「過去にこんな論文の入れ替えはなかった」「リスク評価に偏りがある」専門家たちが問題を次々と指摘/PFAS論文差し替え疑惑・番外編
PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)は、現代社会に遍在する化学物質です。食品包装材、消火剤、衣類の防水加工などに広く使われていますが、環境中で分解されにくい特性から「永遠の化学物質」と呼ばれます。このPFASが人体に及ぼす影響については、長年にわたり研究が進められてきました。しかし、2024年に日本の食品安全委員会が発表したPFASの健康リスク評価では、使用された論文が大幅に差し替えられ、その透明性に疑問が投げかけられています。
PFASが健康にどのようなリスクをもたらすのか、そして評価プロセスの何が問題なのかを、具体的な事例とともに詳しく解説します。特に、論文差し替えが評価にどう影響したのかに注目します。
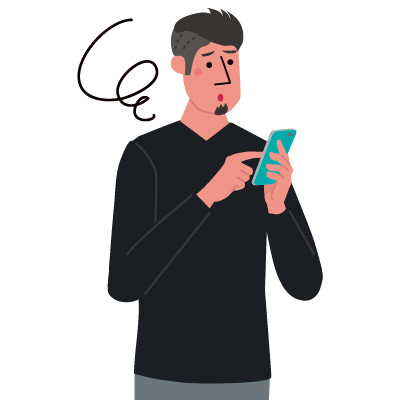
「なるほど…。」
PFASとは何か
PFASは、撥水性や耐熱性に優れた人工的な化学物質で、日常生活のあらゆる場面で利用されています。例えば、テフロン加工のフライパンや防水スプレー、ファストフードの包装紙などに含まれています。しかし、その便利さの代償として、PFASは自然界でほとんど分解されず、土壌や水に蓄積します。 結果として、飲料水や食物を通じて私たちの体内に取り込まれ、長期的な健康リスクが懸念されています。
これまでの研究で、PFASが引き起こす可能性のある健康影響として、以下が挙げられています:
- 発がん性: 特に腎臓がんや精巣がんとの関連が指摘されています。
- 胎児への影響: 出生時の体重減少など、発育への悪影響が報告されています。
- その他の影響: 肝臓障害や内分泌系の乱れなども議論されています。
こうしたリスクは、国際機関でも認識されており、アメリカ環境保護庁(EPA)や欧州連合(EU)では、PFASの規制強化が進んでいます。日本でも同様の懸念が浮上していますが、食品安全委員会の評価プロセスには多くの課題が残されています。
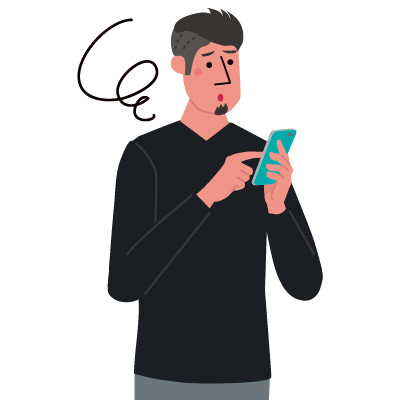
「どんな内容か気になりますね。」
食品安全委員会のPFAS評価
2024年、食品安全委員会はPFASのうちPFOA(ペルフルオロオクタン酸)とPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)の健康リスク評価を公表しました。この評価では、「耐容1日摂取量(TDI)」が以下のように設定されました:
- PFOA: 20 ng/kg/日(体重1kgあたり20ナノグラム)
- PFOS: 20 ng/kg/日
この数値は、主に動物実験のデータを基に算出され、健康への影響を最小限に抑えるための基準とされています。しかし、この評価プロセスには大きな議論が巻き起こっています。特に問題視されているのは、評価に使用された論文の選定方法です。
会見したNPO法人「高木基金」のPFASプロジェクトによると、この耐容1日摂取量20ナノグラムは、米国基準と比べて200倍から666倍高い数値です。
TBS NEWS DIG 「PFASの健康リスク評価 検討過程で参考文献の7割を差し替え 国の食品安全委員会「国側の意向でない」と恣意性を否定」より引用
報告によると、当初選定された257本の論文のうち、190本が除外され、新たに201本が追加されました。つまり、元の論文の約74%が差し替えられたのです。 この変更は非公開の会合で行われ、どのような基準で論文が入れ替えられたのか、その詳細は明らかにされていません。除外された論文には、PFASの健康リスクを強く示す研究が含まれていたとされ、評価の信頼性が揺らいでいます。
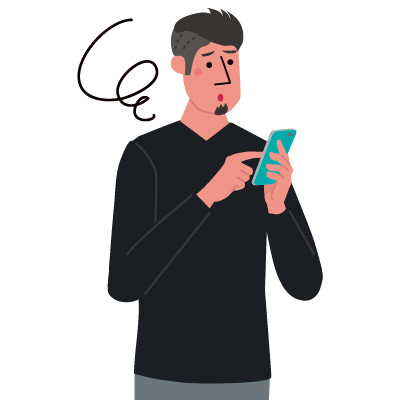
「結構な数の差し替えですね。2024年といえば、PFASの問題はすでに顕在化してましたし、全国的な影響が報道されていましたからね。」
論文差し替え問題の詳細
論文差し替えが特に注目されたのは、健康影響に関する評価です。内容が公開されていましたので、それぞれ具体的な事例を挙げて、問題点を掘り下げます。
1. 発がん性(腎臓がん)
PFASの発がん性、特に腎臓がんとの関連は、国際的な研究で広く議論されています。しかし、食品安全委員会の評価書では、「証拠は限定的」とされ、リスクが十分に反映されませんでした。
具体例:C-8プロジェクト
アメリカのウェストバージニア州で実施された「C-8プロジェクト」は、PFAS製造工場周辺の約7万人の住民を対象にした大規模調査です。この研究では、PFOAへの暴露が腎臓がんのリスク増加と関連していることが示され、EPAや国際がん研究機関(IARC)でも発がん性の証拠として採用されています。しかし、日本の評価書では、この研究が「関連なし」と誤って評価され、除外されました。
採用された研究の問題点
代わりに採用された研究は、EPAが「証拠として不十分」と判断したものです。さらに、この研究はPFAS製造企業による資金提供を受けており、利益相反の可能性が指摘されています。 専門家からは、「健康リスクを示す重要な研究を意図的に無視したのではないか」との批判が上がっています。
国際的な評価との乖離
EPAやEUでは、PFASの発がん性を認め、飲料水基準の厳格化や使用規制を進めています。一方、日本の評価がこれら国際基準と異なる結論に至った背景には、論文差し替えが影響している可能性があります。例えば、EPAはPFOAとPFOSの飲料水基準を4 ng/Lに設定し、厳しい管理を求めています。
2. 胎児への影響(出生時体重の低下)
PFASが胎児に与える影響として、出生時体重の低下が多くの研究で報告されています。しかし、食品安全委員会の評価では、このリスクが軽視されました。
具体例:国際的なメタ解析
23の疫学研究を統合したメタ解析では、母親のPFAS暴露が出生時体重の減少と関連していることが確認されています。この結果は、国際機関でも重要な証拠として扱われていますが、日本の評価書では、関連を示す論文が非公開の会合で除外されました。
評価書での扱い
評価書では、「出生後の長期的な影響が不明」との理由で、出生時体重の低下をTDI設定に反映しませんでした。しかし、出生時体重の減少はそれ自体が健康リスクとされ、国際的な評価では重視されています。 専門家は、「長期的な影響を待つ必要はない」と指摘し、日本の判断を疑問視しています。
論文差し替えの影響
除外された論文には、EPAが「信頼性が高い」と認めた研究が含まれており、代わりに採用された研究では関連が否定されていました。この選定の偏りが、リスクの過小評価につながった可能性があります。
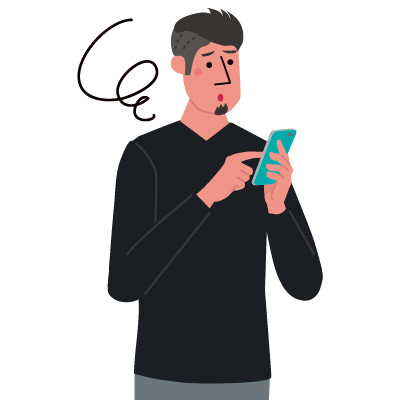
「なんなんでしょう。このような疑義が出てしまうと評価としての信頼性に欠けますね。」
評価プロセスの透明性に関する問題
論文差し替え問題の根底には、評価プロセスの透明性の欠如があります。以下に、具体的な課題を挙げます。
1. 非公開の意思決定
論文の除外・追加は非公開の会合で決定され、その基準や経緯が公表されていません。透明性を確保するには、プロセスを公開し、国民が検証できる形にする必要があります。
2. 恣意的な論文選定
当初の257本から190本が除外され、201本が追加されたこの大幅な変更は、評価の恣意性を疑わせます。科学的な根拠に基づくべき評価が、主観的な判断に左右された可能性があります。
3. 利益相反の懸念
採用された研究の一部は、PFAS製造企業が資金提供したもので、利益相反が懸念されます。評価の独立性を保つためには、こうした研究の扱いに慎重さが求められます。
4. 専門家の批判
多くの専門家が、評価プロセスの透明性と信頼性の欠如を問題視しています。「過去に例のない規模の論文差し替え」「低評価の論文でリスクを否定するのは非論理的」との声が上がり、再評価を求める意見が強まっています。

「なるほど。」
今後の課題
PFASの健康影響と論文差し替え問題を通じて、食品安全委員会の評価プロセスには透明性と信頼性の向上が求められます。論文差し替えにより健康リスクが過小評価された可能性や、非公開のプロセスに対する批判は、国民の安全を守るための評価として見過ごせません。
今後、以下の取り組みが必要です:
- プロセスの公開: 論文選定の基準や差し替え理由を明確化し、検証可能にする。
- 再評価の実施: 除外された論文を含め、総合的な見直しを行う。
- 国際基準との整合性: 海外の知見を参考に、日本の基準を再検討する。
- 利益相反の管理: 研究の資金源を透明にし、独立性を確保する。
PFASは私たちの生活に深く浸透しており、その影響は長期に及びます。だからこそ、評価は公正で透明であるべきです。
【試験結果あり】有機フッ素化合物は浄水器で除去できるか試験 【環境省】有機フッ素化合物の血中濃度の全国調査をみる 残留塩素の基準値に上限がないは本当!?

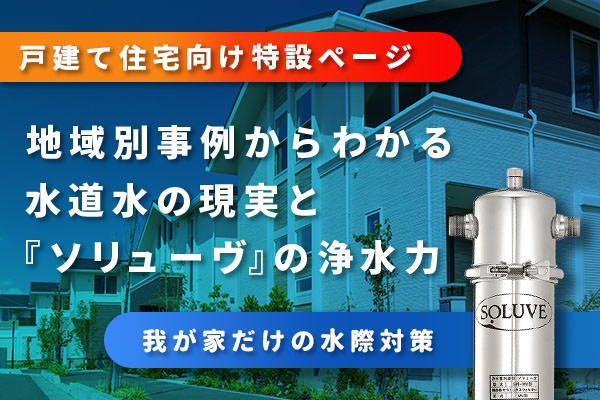

まとめ
「いかがでしたでしょうか。PFAS論文差し替え問題について解説しました。」


「はい。よく分かりました。」
おすすめ関連記事
「以下の関連記事も、是非ご覧ください。」